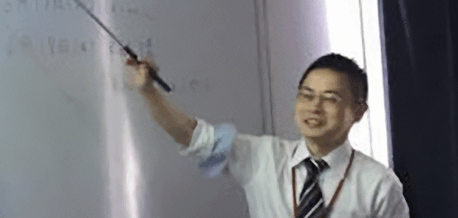再送:米長期債買い入れこうみる:財政ファイナンスの方向性くっきり=バークレイズ 森田氏【ロイター】
先進国はゼロ金利・量的緩和クラブといわれる状況だ。各国中央銀行は信用緩和のメニューはほぼ揃えてきている。財政拡張のなかで結果的には財政ファイナンスになることは否定のしようがない。
珍しく日銀が積極的に動くなぁ、と思っていたらほぼ直後にFRBの政策サプライズ。このタイミングのよさを考えると、日銀とFRBとの間で何らかの連絡があったのではないかともかんぐりたくなってしまいます。
これで、主要通貨を持つ先進各国はユーロを持つEU以外、ほぼ全て量的緩和に突入。量的緩和の先駆者である日銀と、金融危機下の行動力と安定した対応で評価急上昇中のFRB、高金利通貨から数ヶ月で一気に量的緩和へ移行した英国BOE。
逆に量的緩和を実施していないのは、いち早い大幅利下げを敢行して評価を上げ今は最も早く利下げ止めを表明してやはり評価の高いオーストラリアRBA。そして――、やる気のなさと議長のKY振りには定評のある中央銀行の落第生、ユーロ圏ECBです。
こうしてみると、量的緩和を実施しておらず政策能力にも定評があるオーストラリアが強含みに見えますが、現実はそうでもありません。やはり通貨としてみると、流通量が大きく、金利の問題さえなければ安全通貨として使えるユーロが値を上げているようです。
● ドル円
買い方針を維持します。むしろ私は強気です。恐れるな、買え、買うんだ!もっとも言うまでもなく、最低限のチャート型は確認します。
さすがに今朝はビビりましたが、ユーロの大ヒットのおかげでかなり余裕もありますので、ここはしっかり下がったところを買います。ここはしっかりリスクをとっていきたいとおもいます。
目処として示していた96円のレンジ下限は割っていますので判断に迷うのは正直なところですが、94円までは買える水準です。95円台もイイでしょう。ダメなら投げて93円まではととことんやります。もっとも最終防衛ラインは93円ですのでここを割れたら、長期トレンドも変わったと考えます。
ここからは米国の量的緩和 VS 日本海外投資です。
FOMCの件が、単なるイベントサプライズであれば、間違いなく96円水準で思い切った買いをいれていたと思います。ただ、昨年末と同じく量的緩和合戦が市場の話題となるとすれば、単なる一発イベントで直ぐに反発するという地合いではなく、息の長いトレンドを作る可能性もあります。そのため、慎重に買い場を探しているのが今の段階です。
基本的には、今日のロンドンフィックスまでの値動きを見れば、以下のいずれかになると判断できると考えています。
96~99円のレンジに回帰。再び持ち合いを開始した後、放たれて99円を突破する。
94~96円での底固めを開始。底固め後、再び99円チャレンジを再開する。
93円水準に向かって、中期的下落トレンドとなる。
NY終値で95.70を越えていればレンジに回帰と考えます。この場合は、先日のシナリオがそのまま使えます。
「99円を超えられない水準では戻り買いで買いポジションを積み上げ、99.15を超える水準では上値を追って買います。99円以下のポジションの最大下値は96円付近とし、96円で全玉損切りになっても耐えられる範囲でポジションを建てます。もしくは損切りしながら買い下がります。なお、99.15円付近のポジションの下値目処は98.40円とします。
また、94円を含めた底固め、でも買いでいいでしょう。その過程で95円の攻防具合を見れば、93円水準に向かうかどうかは判断できると思います。
基本的には、急落というのは大変買いやすい状況ともいえます。何故なら、徐々に下げられてしまうと、買っては投げ買っては投げの繰り返しで痛手を負ってしまいますが、急落一発であれば損切りが一発発動するだけですから。下値のサポートで買いなおせば、もし本来的なトレンドと外れていたとしても33%戻し位は期待できますから、調整反発だけでも損切り分を回収するチャンスもあります。もっとも急落だけで済まない場合はそもそも長期のトレンドを読み間違えているわけですが。
なお、ドル安が息の長いトレンドになる可能性も考慮して、ドルストレートペアの買いポジションを他に持つことをオススメします。現在のドル買い判断は、米国の量的緩和を日本の事情が上回って円安が進むシナリオです。経済回復=円安の基本法則に変化がない限り、この見通しを維持します。
● 欧州通貨
1.30固めに成功し上昇地合いを作っていたところに、ニュースによるサプライズで次々に売りの逆指値を巻き込んで上昇しました。これは先のドル円急騰と全く同じ構図といっていいでしょう。短期筋の損失確定が急騰に一役買っています。
だからといってここから単純に半値戻しとか、相応の戻りが発生するシナリオが妥当かは難しいところ。先のドル円急騰の際も押し目らしい押し目を作らずに上がり続けたわけですし、無用な予断は持ちたくないところ。こちらは短期で集中力を上げて、しっかり買っては売り、買っては売りを繰り返したいと思います。
そうはながら、当然反落のリスクがありますから、利益確定の逆指し値はこまめに入れていきたいところです。
米国と日本が実質的な量的緩和(つまり通貨安を招く政策)に突入する中、ECBがやる気のなさ全開なことが逆に好感されている状態のようです。まぁ、やる気がないのと、本当にやらずに済むのとでは、また別問題ですけどね。
ところで、昨日のユーロについてはドル円よりも分かり易い水準で固めていましたから、EUR/USDの買いはやりやすかったと思います。私もより分かり易いという理由でユーロ買いに取引の比重を移していたおかげで、ドル円の損失をカバーしてなお大きなお釣りがきました。
正直、夜しかチャートを見る暇のない個人としては、4通貨見てるのは結構大変で、通貨を絞るべきではないかっていう話もあります。そもそも、ドル円とユーロドルをやるくらいなら最初からユーロ円をやっとけ、とか。
ただ、今回のようにドル単体の要因で急落が発生するような局面ではやっぱり、通貨を分産して配分を変えるというやりかたはアリかなと思います。
私のポートフォリオはもうここに書いてあるまんま、USD/JPY、EUR/USD、AUD/USDです。それに加えてその時々で面白そうな通貨をスポットで一つというのが基本的な考え方です。その為、単にドルがドルの要因で急落した場合は、ユーロや豪ドルが支えますし、ドル高が進めばドル円が支えます。
逆に手痛いのは、リスク志向でドル高・円高が同時進行して、かつ売りと買いのトレンドを読み違えている場合で、昨年後半は特にそれでかなりやられましたが・・・・。
それでもこうした分散の考え方は、チャートに張り付いていられない個人投資家には重要だと考えています。
● 豪ドル
こちらもユーロと同様――、といいたいところなのですが0.660の固めに失敗した状態のままから、FOMCのサプライズイベントで一気に上抜けました。確かによく上がってくれましたが、その直前の下落幅をみると最近の豪ドルらしい下値のブレ幅の大きさは顕健在だと改めて感じました。
引き続き買い方向ですが、上述の通り下値のブレ幅の大きい豪ドルは要注意です。短期筋の売りポジションが溜まっていたユーロに比べて、豪ドルは純粋に新規のポジション積み上げで値を上げていると思われます。従って、未だ底堅さには懸念が残る状態ですので、突っ込み買いには要注意です。突っ込んで買うならユーロのほうがいいでしょう。
私は戻りをまって豪ドルを買い積み上げる戦略でいきたいと思います。豪ドルについては、慌てず、買いすぎず、じっくりいきます。ただしオーストラリア自体の事情を見ると、このところ経済指標の上方修正が目立つ米国に比べ、下方修正が目立っているのが気になります。これから秋・冬に突入する豪州は景気活動が停滞しやすい側面がありますので、今日の上げを見て強気になりすぎないように注意したいところです。
長いスパンのポジションの持ち越しは豪ドルの仕事、短期の取引はユーロの仕事、そして全ての源泉はドル円。そいういう使い分けを私はしてます。