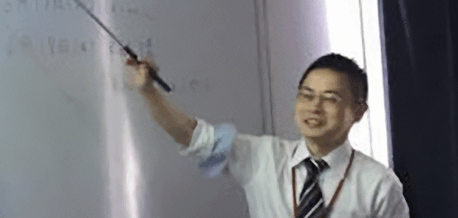私が勝手に「楽天フォーマット」と呼んでいるデザインがあります。
縦に長くて、正直ダサい。けれども商品は驚くほど売れる──あの楽天市場の商品ページのデザインのことです。
そして最近発売されたiPhone17では、あのAppleまでもが縦長スクロールのデザインを採用。デザイン業界でも大きな話題となっています。
今回は、縦長スクロールデザインの歴史を振り返りながら、なぜ“なくなるどころか広がり続けている”のかを整理してみます。
縦長スクロールの系譜
1. ダイレクトレスポンス広告の世界(1950〜70年代、紙媒体)
実はこのルーツをたどると、新聞や雑誌の通販広告に行き着きます。
「ヘッドライン → 悩み提起 → 商品紹介 → 権威性 → テスティモニアル(顧客の声) → クロージング」という一枚完結型のストーリー構成は、すでに紙の時代に完成していました。
日本では「通販カタログ」「チラシ」、アメリカでは「セールスレター」と呼ばれるものです。
👉 つまり「楽天フォーマット」も、この直販広告のDNAを受け継いでいるのです。
2. インフォマーシャル型LP(1990〜2000年代、インターネット黎明期)
インターネットが普及し始めた頃、アメリカでは「ロングフォーム・セールスレター」と呼ばれる異常に長いHTMLページが氾濫しました。
例:健康食品・教材・情報商材など。
特徴は「赤字・黄色マーカー・無限に続くテスティモニアル」。
これがそのまま日本に輸入され、「情報商材LP」や「健康食品LP」として広がり、やがて楽天市場やアフィリエイトの文化に定着しました。
👉 こうして「売れるのはダサい縦長ページ」という文化的刷り込みが日本に根付きました。
つまり、真犯人は楽天ではなくアメリカだったわけです。
3. パララックス・ストーリーテリング(2010年代)
欧米では2010年代に、スクロールに応じて背景や要素が動く「パララックス・スクロール」が流行しました。
象徴的なのは2012年の Snow Fall(New York Times)。縦スクロールをストーリーテリングに活かした代表例です。
これにより「長い=ダサい」から「長い=物語性を演出できるクールなデザイン」へと評価が二分化。
一方、日本ではパララックスはあまり好まれず、代わりに動画をヒーローイメージとしてTOPに置くLPが増えていきました。
4. Apple型プレゼンテーションサイト(2010年代後半〜)
Appleは製品ページを「1スクロール=1メッセージ」という形式に進化させました。
特徴は「シンプルなビジュアル × 精緻なアニメーション × セクション分割」。
これは“楽天フォーマット”と“Snow Fall型ストーリーテリング”を、デザイン的に洗練させたハイブリッドとも言えます。
一方、日本ではさらに動画活用が進み、LP内に複数の動画を埋め込む手法が一般化しました。
まとめると
発祥は 紙のセールスレター広告 → ネット通販LP → パララックス記事 → Apple型ブランドサイト という流れです。
「楽天フォーマット」と「Apple型サイト」は、一見すると真逆のように見えますが、どちらも同じダイレクトレスポンス広告の血を引く兄弟。
違いは「どこまで情報を詰め込むか」と「どれだけ洗練させるか」という美意識にあります。
欧米ではパララックスを洗練させてブランド体験に昇華。
日本では動画マーケティングの進化とコスト効率化が進んだ。
💡つまり、同じ源流を持つデザインが、欧米では“ブランド演出”へ、日本では“売れる仕組み”へと進化したわけです。
これから主流になるのは?
従来は「国ごとの文化」がデザインを分けていました。
しかし今後はビジネス規模によって使い分けられ、国ごとの差異は薄れていくと考えます。
- iPhone17型のサイトは莫大なコストがかかる。
- 楽天フォーマットは極限までコスト効率化されたデザイン。
特に「セールス動画をそのままLPのイメージに転用する方式」はコスパの最適解であり、遅かれ早かれ世界的に広まっていくでしょう。
一方、コスパを最優先にしたデザインは、ブランドイメージを損なうリスクがあるのも事実。
十分な予算を投じられるブランドサイトでは、むしろ iPhone17型のロングスクロール がさらに洗練され、体験型デザインとして進化していくと考えられます。