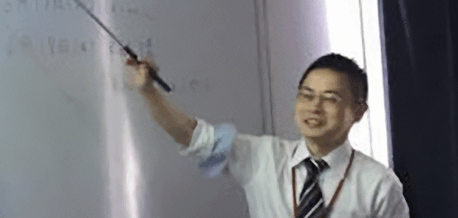私はこれまでコンサルタントとして、企業に対してBIなどを活用したシステム提案を行ってきました。しかし最近、「ExcelとChatGPTだけで十分では?」と改めて感じています。
今回は、AIと会計・監査の関係について整理し、「ワークマンのExcel経営術」のコンセプトの正しさについて改めて考えてみようと思います。

1. AIは会計処理には向かない
会計は1円単位での厳密性が必須です。
一方、AIは内部的に「確率的な処理」を行っており、同じ質問でも答えが変わることがあります。
これはAIが半精度浮動小数点演算という、サイエンスの教授が卒倒するような酷い精度の演算を使っていることに理由の一つがあります。
AIのデータはあまりに膨大で、従来の演算では処理しきれません。そのため近年、CPUやGPUに半精度浮動小数点演算器という荒い計算を高速に行う機能が実装されました。
- 整数演算(会計システム)=電卓やExcelを使う → 常に正確
- 倍精度浮動小数点(FP64)=大学数学専攻レベル → かなり精密で科学計算に耐える
- 単精度浮動小数点(FP32)=高校生の計算力 → 桁数も小数もある程度正確
- 半精度浮動小数点(FP16)=小学生の暗算レベル → 速いけど誤差が大きい
大げさに言うと、AIに仕訳や帳簿の最終処理を任せるのは「小学生の暗算力で財務諸表を作る」のと同じです。
会計処理は従来のシステムに任せるべき分野です。
2. 不正検知にはAIが向いている
一方でAIが得意とするのは、異常の兆候を見つけることです。
- 売上や利益の不自然な急増
- 営業CFと純利益の乖離
- 数字の分布が不自然(Benfordの法則に違反)
- 期末に偏る売上計上
こうした「赤信号」を探すのは統計処理的アプローチであり、少々の誤差が許される領域です。AIはここで威力を発揮します。
決算で1円の誤差が出たらメチャメチャ困りますけど――、統計・監査の世界で1銭の違いを争っても仕方ないですからね。
3. Excel+ChatGPTで監査は可能
難しいシステムを導入しなくても、普段のExcel集計データをChatGPTにアップするだけで、AI監査は実行できます。
例えば:
- 「前年同月比で急増している科目は?」
- 「営業CFと利益の乖離を抽出して」
- 「不自然に丸められた数字が多いか?」
こうした問いにすぐ応答でき、しかもサマリ付きでレポート化まで可能です。
白状すると私も今まで、コンサルとして偉そうに「BIで海外法人の不正を検知出来ます!」とかいってシステムを売っていました。
いや、ちゃんと検知出来ますよ。できますけど…、BIって使う側に負担を掛けます。その点、ChatGPTの方がカンタンです。
私は「複雑で面倒なシステムを顧客に売るのは、システム屋の責任の押しつけ」だと思ってます。
どうせ事故が起きたら「貴方の使い方が悪い」とか言うんでしょ?
4. ワークマンのExcel経営術の再評価
ワークマンはERPやBIに頼らず、Excelを徹底活用することで有名です。
AI時代に入って、この考え方は価値を失うどころかいっそう正しさが証明されています。
- 高価なシステムを導入するよりも
- 現場がすぐに使える仕組みを整える方が効果的
そしてとうとう、ExcelをChatGPTにアップするだけで売上予測や監査まで出来るようになりました。
今、BIシステムで監査をしている方は、出入りのベンダーにシステムのバージョンアップ見積を取って見てください。いったいいくらの見積が返ってきましたか?
ワークマン方式ならChatGPTを有償版にして、ドラッグ・アンド・ドロップするだけです。
5. Excel方式のリスク
しかしこれでは私の仕事がなくなってしまいます…
ExcelとChatGPTだけでは限界もありますので、そこをお伝えさせてください。
- 属人化しやすい(担当者依存)
- 教育コストがかかる
- 集計工程そのものに不正や誤りが紛れ込むリスク
便利でスピーディな反面、上司が結局リスク管理する必要があります。
Excelを使う人が不正を行ったら…、ワークマン方式は破綻します。
ワークマンの場合、各店舗の店長、即ち経営者がExcelを使うからリスクがないのです。フランチャイズだからこそ出来る事です。こうして考えても、ワークマンのExcel経営術の制度設計の美しさは凄まじいものがありますね。
そして残念ながら、多くの企業はそれを真似することは出来ません。
6. 規模が大きくなればシステム化が有効
海外法人や複数拠点を抱える企業になると、Excel方式では追いつきません。なにより監査工程での不正を防ぐにはシステム化するしかないのです。
そこで、Vertex AIのような基盤を使って監査フローをシステム化するのが効果的になるわけです。
- データを自動で収集・整理
- AIが異常をサマリして経営層に報告
- 忙しい経営者でも数分で全体像を把握
こうしたスケーラブルな仕組みが、システム化によって実現できます。
しかもExcelの使い方を新入社員に教える必要もありません。私、新卒で入った会社は富士通の教育部門で、インストラクターをやっておりました。Excelを教える大変さは重々承知しております…
まとめ
- 会計処理の厳密さはAIには不向き
- 不正検知や傾向把握はAIの得意分野
- 小規模ならExcel+ChatGPTで十分
- 大規模ならVertex AI等でシステム化
つまりワークマンの「Excel経営術」的アプローチに学びつつも、実際には「AIシステム化」が多くの企業では必要となります。
皆様もまずはExcel活用を試してみて頂き
「面倒くさっ!!」と思ったら私にご相談いただければ幸いです。
補足 – AIの演算について
冒頭で半精度浮動小数点演算について触れましたが、「LLMの学習段階」と「推論段階」では扱う数値表現が違います。分かりやすさを重視してあのように書きましたが、技術的・学術的には不正確な面があるので補足させてください。
実際には最終段階では精度の高い演算が行われるように工夫されていて、会計処理にはまだ厳しくとも、多くの用途で不便ない程度の精度が出るようになっています。
理すると以下のようになります。
1. 学習段階(Training)
- LLMの学習では、膨大な行列演算を何週間も回す必要があります。
- この時は「計算速度」と「メモリ効率」が最重要なので、半精度浮動小数点(FP16やbfloat16) が主に使われます。
- 多少の誤差があっても学習全体で平均化されるので問題になりにくい。
- 最近は 混合精度学習(mixed precision) が主流で、重みは半精度、勾配や累積は単精度(FP32)で保持する手法も多いです。
2. 推論段階(Inference:Excelをアップして判断する段階)
- モデルに学習済みパラメータを読み込んで実際に応答を生成するプロセスです。
- このときの演算も効率化のため INT8量子化 や FP16 がよく使われます。
- ただし、最終的にユーザーに返すテキストや分析結果は CPU上でFP32(単精度)や整数演算に変換 されて処理されます。
- つまり「Excelの数値をそのまま壊す」ことはなく、推論出力の段階では単精度に相当する安定性 が確保されています。
3. 実務的な意味
- ChatGPTにExcelを渡して「このセルの合計は?」と聞けば、誤差1円レベルで間違うことはまずありません。
- ただし、これは「算数問題」としての精度であり、会計帳簿の正確性を保証するわけではないのが重要です。
- 会計処理は厳密に整数演算で行う必要がある一方、LLMは 最終的な判断やレポート化の支援 に活用するのが適切です。
まとめ
- 学習時 → FP16やbfloat16など半精度が中心(効率重視)
- 推論時 → INT8量子化やFP16を使うが、最終出力はFP32相当の精度で安定
- ユーザー視点 → ExcelをChatGPTに渡して判断する際は「単精度浮動小数点演算レベルの精度は確保されている」と考えて差し支えない