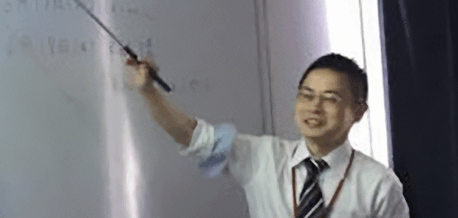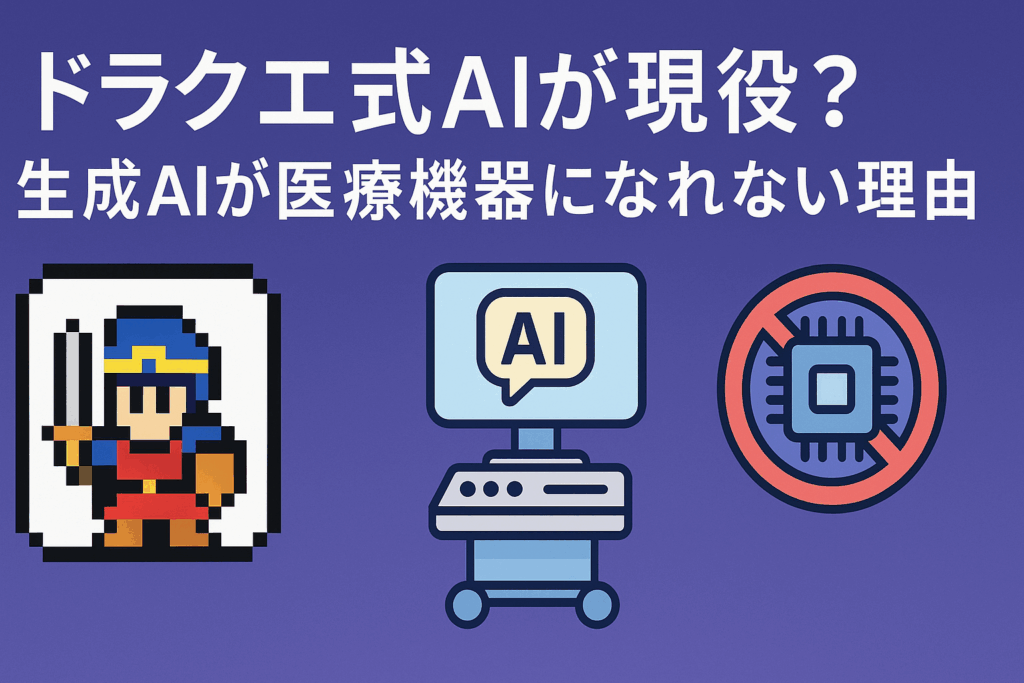
はじめに
病院には様々な医療機器が導入されています。多くの人がまず思い浮かべるのは、CTのような何億円もする巨大な装置でしょう。
しかし、いまや「ソフトやアプリも医療機器として認証を受ける」時代なんです。
実際、画像診断支援ソフトや心電図解析アプリはすでに薬機法のもとで承認を受け、医療現場で日常的に活用されています。
では、ChatGPTに代表される生成AIや大規模言語モデル(LLM)を利用したアプリは?
残念ながら現行制度の枠組みでは、「医療機器として認証を受けるのは極めて難しい」と言わざるを得ません。
本記事では、私自身が『糖尿病患者向けの食事指導AI』や『身体測定データに基づく健康指導システム』のコンサルティング・開発に携わった経験を踏まえ、
- なぜ生成AIが医療機器認証を受けにくいのか
- それでも医療やヘルスケア分野でどう活かす道があるのか
についてお話ししていきます。
医療機器の認証とは
日本人は権威が大好きです。医療ビジネスの権威の極致とも言えるのが「国の医療機器認証」でしょう。はい、私も大好きです。強そうでいい。
その信用を守るため、医療機器は厚生労働省・PMDAによる厳格で保守的な審査を受ける必要があります。審査で重視されるのは以下の3点です。
- 安全性:誤作動や誤診によるリスクがないか
- 有効性:医療上の効果が客観的に証明されているか
- 再現性:誰が使っても、いつ使っても同じ結果が得られるか
これらは「患者の命に直結する領域」である以上、極めて厳格に求められます。
なぜ生成AIは認証されにくいのか
1. 出力が確率的で安定しない
LLMは「確率的に最もらしい回答を出す」仕組みであり、同じ質問でも結果が変わることがあります。これは「一貫性・再現性」を求められる医療機器の基準とは相容れません。
また別の記事でも書きましたが、LLMでは半精度浮動小数点演算と呼ばれる計算が用いられています。医師の方なら「そんな精度で大丈夫なのか?」と驚かれるかもしれません。
2. ブラックボックス性
生成AIはなぜその結論に至ったのかを人間が説明できません。すべてを確率と統計で処理し、その演算精度も限定的です。
医療機器は「アルゴリズムや根拠を明示できること」が求められるため、この不透明さは大きな問題となります。
3. 学習データの不明確さ
LLMは公開情報を含む膨大なデータを学習していますが、その正確性や出典を保証できません。誤情報が紛れ込むリスクがある以上、医療現場で使う機器としては承認が困難です。
実際には「特化型AI」というビジネスジャンルがあり、ここでは「何を学習させるか?」に大きなノウハウがあります。小さな企業が大手を上回る品質を出すことも珍しくありません。
しかし医療分野に限って言えば、ただでさえ多忙な研究者に膨大なデータの取捨選択を任せるのは現実的に難しいのです。
認められるAIと認められないAI
現在すでに承認されているAI医療機器も存在します。共通する特徴は次のとおりです。
- 特定の用途に限定されている(例:肺がん診断支援、糖尿病性網膜症の画像解析)
- 性能を定量的に検証可能
- 同じ入力には同じ出力が得られる
つまり、「万能型」の生成AIではなく「目的特化型」のAIに限って承認の道が開かれているのです。
そして、こうしたAIは例外なくルールベースAIという手法が採用されています。
ルールベースAIとは、人間が定義した条件分岐や知識ベースに基づいて判断する仕組みです。例えるなら、1988年に発売された『ドラゴンクエストIV』に搭載されていた戦闘AIと同じ発想です。
厳密性を求められる医療分野では、最新の生成AIではなく、35年以上前から存在する古典的な手法が今なお現役で使われています。
この文化は医療だけではありません。金融分野でも同様に、「失敗できない領域」では革新的な技術より「実績と安定!」な技術が選ばれる傾向があります。
要するに、リスクを最小化することこそが最大の要件であり、これが生成AIが医療機器認証を受けられない最大の理由です。
実際に私が携わった案件でも、最終的実装は結局ルールベースAIに落ち着きました。
ちなみに、ルールベースAIの開発は決して容易ではありません。
「ルールすべての品質を担保する業務フロー」が必要で、技術的課題だけでなく人的・組織的な問題にも向き合うハメになります。
今後の展望
では、生成AIは医療分野で全く役に立たないのでしょうか?
これからも古典的なルールベースAIをメンテする苦行が必要なのでしょうか?
いいえ、そうではありません。業務の効率化に有効であるのは医療も同じです。
- 医師の記録作成を効率化する
- 患者説明資料を平易な言葉に書き換える
- 医療機器として承認済みAIの結果をわかりやすく補助する
また、「0か100か」で考える必要もありません。LLMとルールベースを組み合わせることで、新しい可能性が開けます。
実際、私は医療機器認証の要件と正確性を担保しながら、その中でLLMを活用するためのコンサルティングを行っています。
まとめ
- 医療機器の承認には「安全性・有効性・再現性」が必須
- LLMや生成AIは出力の揺らぎや不透明さのため、認証要件を満たしにくい
- 承認されるのは「特定用途に特化したAI」のみ
- 生成AIは「医療機器」ではなく「周辺業務の効率化」で活躍が期待される
- LLMとルールベースを組み合わせることで両立の道もある
医療ITのビジネスは現在も立ち上げが活発です。私の元にも台湾企業から「予約診療アプリを展開したい」という相談が寄せられています。
いつまでも日本的な保守性にとどまってはいられません。医療業界にも、より先進的なチャレンジが迫られています。
結局ルールベースAIでアプリをリリースしてしまった私自身も偉そうな事は言えませんが
「古典的手法に頼るばかりでは限界がある」と痛感しています。
だからこそ、生成AIと既存技術をどう組み合わせるかが、これからの医療AIの最大のテーマになるでしょう。