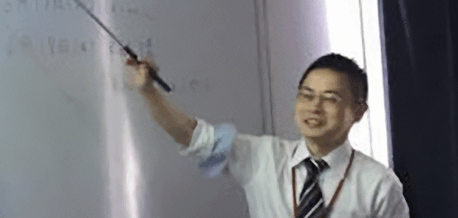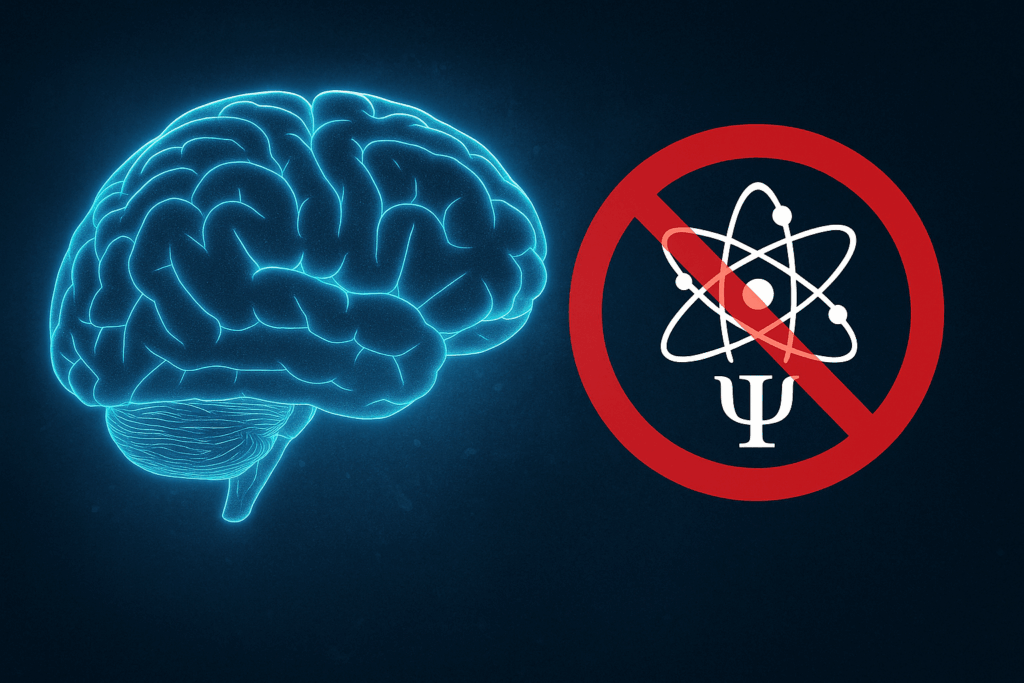
長年、「人間の脳は量子演算をしている」という仮説が語られてきました。
その根拠のひとつが「人間だけが因数分解を直感的に素早くできる」という点です。
しかし私は最近、この説はほぼ否定できると考えています。
なぜなら、量子演算を持ち出さずとも、脳のアナログ回路理論で十分説明できるからです。
1. なぜ「量子脳」説が生まれたのか
私も正直、最近まで人間の「脳は量子演算をしている」と信じていました。
とくに因数分解の話題はその根拠のひとつでした。
因数分解は既存のコンピューターが大の苦手とする分野です。
あまりに因数分解が苦手すぎて、多くの暗号技術で「コンピュータは因数分解が遅い」ことを利用した暗号化が行われているほどです。
RSA暗号が発明されてから約半世紀。RSA-2048は未だ破られていません。
この前提を破壊してしまうのが量子コンピューターです。
量子コンピューターは将来的には現代の暗号を一瞬で解読出来ると言われています。
しかし――、
人間も高校数学レベルの多項式の因数分解なら「パッと見て」答えられる人が多くいますよね?
そう、ここに量子コンピューターと人間の共通点があるのです。
しかしおそらく、人間は量子演算をしているわけではありません。
脳のアナログ回路を使って直感的な「パターンマッチング」していると考えられます。
2. 実はそんなに凄くない、量子コンピューター
今の量子コンピュータと暗算の速い高校生が因数分解を競ったらどっちが早いと思いますか?
結論から言うと、現状の量子コンピュータと暗算の速い高校生が因数分解で競ったら、高校生の方が圧倒的に速いです。
現在の量子コンピュータの限界
- 実証されたShorのアルゴリズムの規模→
IBMやGoogleなどの実験で因数分解できたのは、せいぜい 15や21といった二桁の整数。 - 理由は、エラー率が高く、安定して動作できる「論理量子ビット」がまだ数十個レベルだからです。
- RSA-2048のような大きな数はおろか、高校数学で扱う4桁〜5桁の数ですら因数分解できません。
高校生の暗算能力
- 因数分解(素因数分解)は、工夫や経験で小さな数なら高速にできます。
- 例えば 12321 = 111 × 111 などは数秒で気づける場合もありますし、数百程度なら試し割りで数十秒。
- 4桁や5桁でも、素因数が小さければ1分以内に解けるケースは多い。
- つまり「高校数学の範囲の整数」なら人間の方が圧倒的に有利。
どちらが勝つか?
- 小さい数(高校数学レベル:数桁〜十数桁) → 高校生が圧勝
- 大きな数(数百桁以上、RSA級) → 高校生は全く太刀打ちできないが、量子もまだ解けない
- 未来(数百万〜数億の安定量子ビットが実現した場合) → 量子コンピュータが人間を超えるかもしれない
量子コンピュータは「理論的には大数因数分解に最適」ですが、実際の性能は「九九の練習レベル」です。
3. アナログ回路理論での説明
一方人間は、量子演算を使わず「アナログ信号の干渉」を利用していると考えられます。
因数分解などの問題を次のように処理している可能性があります。
- パターン共鳴(resonance)
入力された数式や整数に対し、既知の「因数候補」パターンが同時並列で活性化し、最も共鳴するものが浮かび上がる。
→ これはデジタル探索ではなく、アナログ信号の「強度の干渉」で一発で決まる。 - 連続的アナログ表現
デジタル計算では「1つずつ割ってみる」操作になるが、脳は「数列や式をベクトルとして埋め込み、分解可能性の高い方向に滑らせる」ことができる。
→ まさにLLMがトークンを連続ベクトルに埋め込んでいるのに近い。 - ノイズ耐性
アナログ回路なので、多少のノイズ(例:数値が大きい、係数が見にくい)でも「近い因数形」を候補に出せる。
デジタル計算機なら完全一致を探す必要があるが、人間は「近似因数分解」的な直感をすぐ出せる。
4. なぜ既存の計算機で出来ず、人間には出来るのか?
最近はAIで何でも出来る気がする世の中です。
しかし人間とAIの間には「感覚器の有無と、それを活かした学習機構」という果てしなく埋めがたい差があります。
人間は既存の技術では到底到達できない処理回路を感覚器からの学習を通じて作り上げているのです。
- 言語的パターン学習
数学教育を通じて「典型パターン」(例:平方の形、和と差の積など)を脳内に辞書化している。 - アナログ的並列処理
パターン候補が同時に活性化し、干渉によって最も適合する因数が「一瞬で見える」。 - 効率的な削除
合わない候補はすぐ消え、残ったものが強調される。これはアナログ回路の「不要信号の自然減衰」に近い。
要は人間が因数分解を素早く行える理由は、
- デジタル計算の逐次探索ではなく、
- アナログ的な並列共鳴回路で候補を同時に走らせ、
- 最適なものが自然に浮かび上がる仕組み
これで説明が出来るのです。
「人間の脳=量子コンピュータではないか?」という仮説は長らく人気がありますが、上記のようにアナログ処理で十分説明できる部分が多く、その上今のところ量子コンピュータより高性能です。
5. 結論
ただし、「量子脳」仮説が完全に消えたわけではありません。
- 微小チューブ(微小管=microtubules)内部での量子効果
- シナプス伝達の確率過程に量子コヒーレンスが寄与している可能性
- 無意識レベルでの「直感の非決定性」
これらはは、まだ実証も否定もされていません。量子仮説が完全に消えるわけではなく、まだ未解明の領域は残っている。
しかし、これらは研究テーマとしては興味深いですが、我々実務家には大きなインパクトをもたらさないものです。
そして、何より。人間らしいミスや曖昧さ、そして天才的閃きも全て、アナログ回路理論の方が整然と説明出来ますよね?
人間の脳は量子演算など使わずとも、本来的に量子コンピューター以上の可能性を秘めていた。
こう結論すべきではないでしょうか?