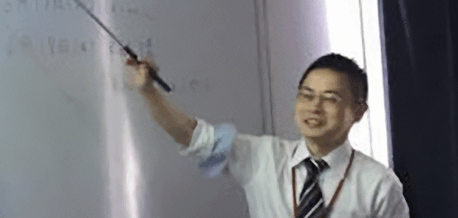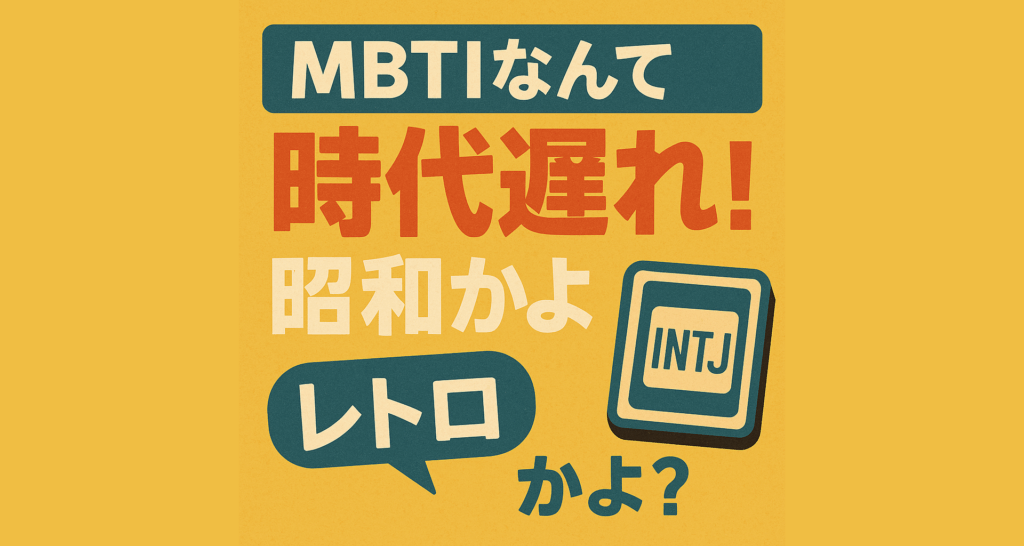
白状します。
私、MBTIなんて最近まで知りませんでした。
性格診断、多すぎやろ?
いったい何種類作れば気が済むんですか?
🧠 まだMBTIで盛り上がってるの?
「あなた、INFPっぽいよね〜」
「いや、オレINFJなんだよ〜」
……楽しいですよね。
血液型占いが楽しいように、MBTIも楽しい。
ちなみに私は「INFP」だそうです。
でもね、MBTIに限らず、ほとんどの性格診断が共通の致命的欠陥を抱えています。
今日はその中でも、MBTIの「最後の一文字」――つまり分類思想の“設計思想”に注目して、
なぜこの考え方がもう時代遅れなのかを説明します。
🧩 MBTIの限界:人を「独立した機械」として見ている
MBTI(Myers–Briggs Type Indicator)は1940年代のアメリカで生まれた理論。
そう、昭和です。
いや、私も昭和好きですよ。
でもね――この理論の根っこにある思想が問題なんです。
MBTIや古典的経済学(合理的選択理論)は、
「個人は独立した意思決定主体である」
という前提で作られています。
人間は内部に「動機」「感情」「判断」を持ち、
外部環境はその“入力”にすぎない。
つまり、「人間=独立した意思マシン」モデル。
これは産業社会の個人主義・合理主義と相性が良く、
20世紀のビジネス理論(組織論・人材管理・マーケティング)を支えてきました。
しかし今や、この前提がすでに崩れています。
今のデジタル社会・ネットワーク社会・AI社会では、
もはや「人の心」と「環境」を分けて考えること自体が、時代遅れなんです。
🌐 心は非合理、環境は合理。それは本当か?
近年の行動経済学や神経科学では、
「人間は合理的に意思決定しない」ことが常識になっています。
ノーベル経済学賞も今や、「非合理」を扱う行動経済学の研究者が中心です。
そしてAIの発展を見ればわかるように、
人間の論理的思考の仕組みは、ほぼ解明されています。
倫理的な配慮から直接そう言う人が少ないので、
空気を読まない私が代わりに言います。
人間の論理的思考の仕組みは、もはや解明された。
残されたのは、“環境と心理”の相関です。
人の心も社会の構造も、
今やひとつの統合理論として扱うことが可能になった。
マーケティングではすでに常識です。
「人の心理」も「社会の動き」も、
一貫したモデルの中で説明できるようになっているのです。
⚙️ 人の心も今やデジタル化可能
デジタル技術の本質とは何でしょうか?
それは「アナログデータを細分化し、人間が扱えるようにしたもの」です。
画像も音楽も、ファイルサイズを大きくすれば綺麗になりますよね?
人の心も同じです。
MBTIなんて、4bitの性格データみたいなもの。
ファミコンです。昭和かよ。
性格診断とは、自分の性格をレトロゲーのドット絵レベルに落として、
その粗さを「わかりやすい!」と楽しむ娯楽です。
でも、現代は違う。
AIと機械学習を使えば、もっと高解像度に人間を理解できる。
たとえば私は、顧客の購買履歴と天気のデータを組み合わせて、需要を予測しています。
これはまさに「心理のデータ化」です。
今や、機械がその相関を自動で見つける時代です。
「人がどんなタイプか」なんて定義をわざわざ作る必要はないのです。
内向的な人と外向的な人、どちらが天気に影響されやすいと思いますか?
今のビジネスにおいて、そんな区別に意味はないのです。
💼 現代のビジネスマンが持つべき視点
私は十年以上、システムのプレゼン資料にストーリーテリングの手法を導入してきました。
これは海外では当たり前の技術で、正直私もパクりです。
でも、今や明確に感じます。
ビジネスでは「心理」と「ロジック」を分けて設計する時代は終わった。
以前の私は「合理的なシステムの前では人はひれ伏す」と信じていました。
しかしその思想では、もう現代の戦場では戦えません。
レベルが低すぎるのです。
これからのビジネスでは、
- 個人がどう感じているか?
- その感情はどんな環境設計から生まれているか?
- どう介入すれば人と社会の関係が動くか?
――この三点を理解しなければ勝てない。
もはや“4bitの時代”は終わりです。
ビジネスでは、高解像度な人間理解が求められている。
🚀 結論:「MBTIは楽しい。でも、古すぎる」
もちろん、MBTIは楽しい。
でもあくまで娯楽です。
問題は、それを信じすぎて、
「人の心理と社会の合理を、一体の理論として理解する」
という現代的な視点を見失うこと。
私は特別なことを言っているわけではありません。
最新の行動経済学に基づいた、ごく教科書的な話をしているだけです。
その考え方を、昭和の分類理論で上書きしてしまうのは危険です。
もう、“人の内面”と“社会”を分けて語る時代ではありません。
新しいビジネスの競争は、すでに始まっています。