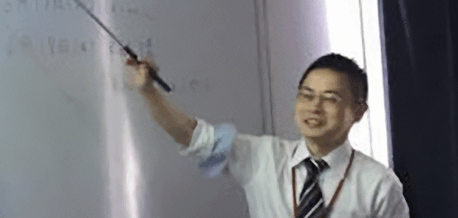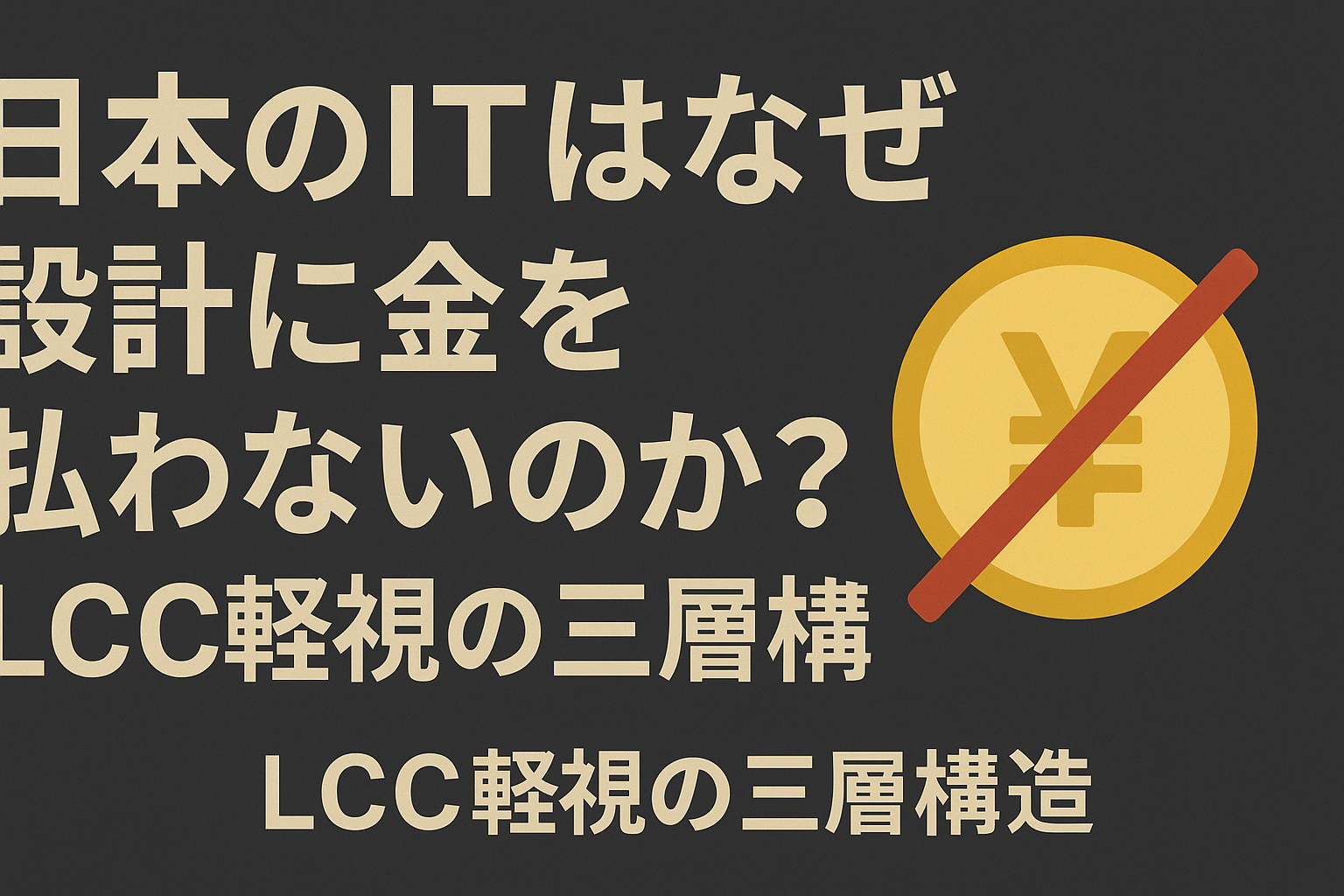
はじめに
建築業界では、2000年代以降「ライフサイクルコスト(LCC)」という概念が定着しました。
建設費だけではなく、維持管理や改修まで含めた総コストを基準に意思決定を行う仕組みが、会計制度や公共調達制度の中に組み込まれたのです。
その結果、建築業界のエンジニアや担当者は、当たり前のように「LCCをどう削減するか」を考えるようになりました。
では、IT業界はどうでしょうか?
驚くべきことに、日本のITエンジニアの多くは「LCC」という言葉すら知らないのが現実です。
戦略コンサルと「権威のビジネス」
私は野村総合研究所にいた頃、「答えは顧客自身が持っている。ただ言語化できていないだけ」という思想を叩き込まれました。
実際ヒアリングしてみると、どのクライアントも例外なく自分たちで課題に対する答えを持っていました。
ではなぜ企業は大金を払って戦略コンサルを雇うのか?
その理由は「権威の購入」だと私は思います。
- 「マッキンゼーがこう言った」
- 「デロイトの分析である」
といった外部ブランドの後ろ盾があって初めて、社内会議や株主説明を突破できる。
戦略コンサルの最大の価値は「答えを出すこと」ではなく、答えを権威化することにあります。
――そんな目的で活用されていた戦略コンサルですが、近年はシステム導入にまで口を出すのが一般的になりました。
システム開発費は高騰の一途。大きな投資を通すためには「戦略コンサルの権威」が必要、という経営会議の事情もあるでしょう。
その延長で、戦略とシステム設計をひとまとめに依頼したくなるのも人情です。
IT業界に欠けているLCC視点
しかしここで問題が生じます。
戦略コンサルが助言するシステム導入は、日本の悪い商習慣をそのまま引き継いでしまっているのです。
それが「ライフサイクルコスト(LCC)を全く考慮しない」ことです。
建築では当たり前のLCCが、IT業界ではほとんど考慮されません。
理由は明快で、会計制度と調達制度がLCCを求めていないからです。
- 開発費(CAPEX)と運用費(OPEX)が分断されている
- 調達は「初期の開発費が安いかどうか」だけで判断される
- 担当者の評価も「年度予算を守ること」に縛られている
これでは、LCCを低減するモチベーションが働くはずもありません。
その結果、現場では何が起きているのか?
誰よりも現場を大切にしているコンサルだと自負している私が、その事情を代弁させていただきます。
三層構造の因果連鎖
LCC不在の「戦略」は、階層をまたいで問題を波及させます。流れを追うとこうです。
- 戦略コンサルがLCCを考慮した設計コストを軽視する
- ベンダーは見積を安く見せるため設計工数を削る
- 設計者の人件費は高いままなので、他の項目に紛れ込ませて帳尻を合わせる
- 現場のエンジニアはその辻褄に目を奪われ、短期リリースに全力を注ぎ、設計より火消しを優先する
- 設計担当エンジニアでさえLCCを考える余裕を失い、短期最適化に流される
この流れを整理すると、三層構造が浮かび上がります。
- 戦略コンサル層
- LCCを考慮した設計投資を「戦略コンサル費」にすり替え、実際の設計投資を軽視する。
- ベンダー層
- 顧客要求に応じ、見積で設計工数を削り、人月換算のプログラミング工数に付け替える。
- 現場エンジニア層
- 設計不足を吸収するため、設計者自身が火消しプログラミングやテストで帳尻を合わせる。
三層が悪意なく複雑に連携しながらLCCを破綻させている。
いわば「関係者みんなが犯人」の構造です。
ただし「誰が一番悪いか?」と聞かれれば、私は間違いなく「戦略コンサル」と答えます。
何故なら「戦略」とは全体的な方針や長期的な計画の事だからです。
「戦略」を自称しながら長期的なコスト構造(LCC)考慮しないのは「優良誤認表示」の謗りを受けても仕方ありません。
戦略コンサルは、長期的視点をを経営者に説くべき立場ではなかったのでしょうか?
戦略コンサルなんてAIで十分?
冒頭で述べた通り、戦略コンサルの最大の価値は「答えを権威化すること」です。
そして「答えは顧客自身が持っている。ただし言語化できていないだけ」というのも事実です。
この役割、AIでもかなりの部分が代替可能になりつつあります。
生成AIは膨大な情報を整理し、一貫したストーリーを組み立て、資料化する能力に優れています。
ただしAIは「一般論の答え」しか出せません。
現場の情報や空気感を捉えて、戦略を実装に落とし込むことは苦手です。
だからこそ人間コンサルの価値は「現場を歩き、観察し、実装に落とし込むこと」にあるのです。
権威付けの代替手段
もし「権威」が必要なら、必ずしも戦略系コンサルである必要はありません。
例えば野村総合研究所(NRI)のように、シンクタンクの調査力とSIerの実装力を兼ね備えた組織もあります。
彼らは「運用フェーズがメイン」というビジネスモデルもあり、自分たちが楽をするためLCC的観点を徹底的に考慮しています。
まぁ、その分「安い」とはいえないので本末転倒かもしれませんが…
海外では、AIをブランド化・権威化する議論も進んでいます。
そういえば、アニメ「エヴァンゲリオン」では3つのAIの合議に人間が従っていました。
あんなSFとまで行かずとも「IBMの量子スカラーハイブリッドコンピューターのAIではじき出した結果」とか言われたら権威性を感じませんか?
実際、IBMは量子演算をAIに導入する試みを行っています。
もう権威はIBMから買えば良いのではないでしょうか?
おそらく、将来的にはその方が安いです。
経営層のコミットメントがすべて
私が前職のセールスやアニメの話をしたかったかのようですが、もちろん結論はそんなところにはありません。
設計軽視の連鎖は全ての関係者に責任がありますが、根本原因を突き詰めると、経営層がLCCにコミットしていないことに行き着きます。
- 経営層が短期的な開発費しか見ず、長期的なコストを軽視する
- ベンダーは価格競争に勝つため、設計工数を削ってしまう
- 戦略コンサルも本来はLCCを訴えるべきだが、その能力もモチベーションも持たない
「戦略コンサルに金を払い、LCCのための設計には金を払わない」という日本ITの矛盾は、制度・文化・慣行が積み重なった必然ですが、その矛盾の代償を払うのは、いつも顧客自身です。
被害者である経営者自身が意識を変えていくべきではないでしょうか?
経営者が視点を変えれば、権威のためにコンサルに金を払う必要はなくなります。
権威のためにNRIやIBMに金を払う必要もありません。
コンサルに「権威の提供」を求めることを止め、AIを活用しつつ現場目線で長期的なコスト削減にコミットできる人材に仕事を任せるべきです。
その仕事を任せる先が我々のようなITコンサルであれば嬉しい限りではありますけれど、御社の中ににそれが出来る方は隠れているはずです。